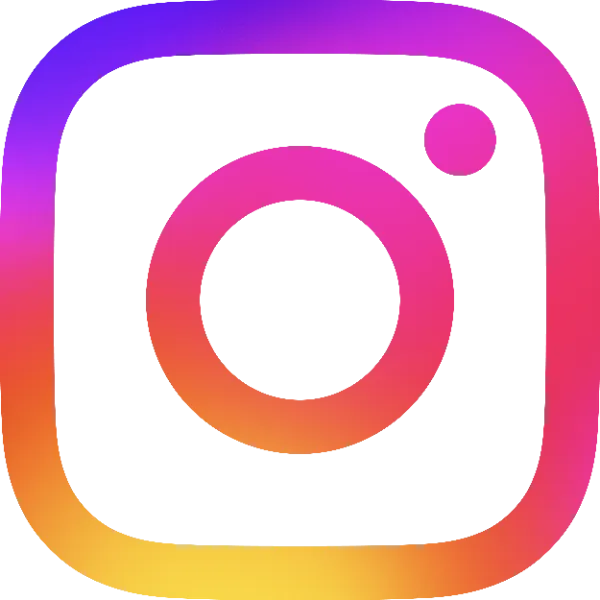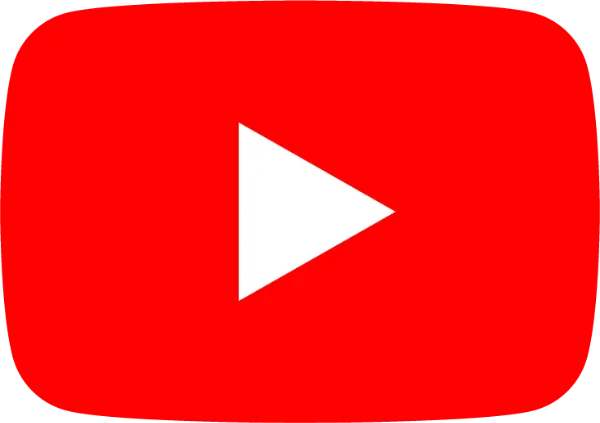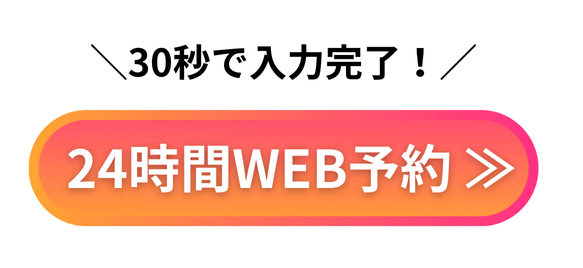「歯が浮いた感じがして噛むと痛いのはなぜ?」
「虫歯じゃないのに、食べると歯がズキッとする…」
そんな疑問や不安を解決します。
この記事でわかること
- 歯が浮いた感じ・噛むと痛い原因11パターン
- 歯医者に行くべき症状の見極め方
- 今すぐできる対処法と市販薬の使い方
歯が浮いたような感覚や噛んだときの痛みには、はっきりとした理由があります。
仕事や家事が忙しいと、つい「そのうち治るかも」と様子を見たくなりますよね?
でも、放置すると悪化したり、治療が長引いたりすることもあります。
この記事を読むことで、「自分の症状はどこに当てはまるか」「まず何をすればいいか」がはっきりします。
歯医者に行くべきか迷っている方や、自宅でできる対処法を探している方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
歯が浮いた感じ・噛むと痛い症状の主な11原因

歯が浮く感覚や噛むときの痛みには、虫歯だけでなく、思わぬ原因が潜んでいます。
身体の不調や癖、他の病気の影響が歯の違和感として現れる場合もあります。以下で代表的な原因を詳しく紹介します。
歯根膜炎(噛むと痛む鋭い痛み)
歯の根を包む「歯根膜」が炎症を起こすと、歯が浮いたような感覚や鋭い痛みが出ます。
原因としては、硬い物を噛んだ衝撃や治療後の刺激などが挙げられます。
炎症が軽ければ自然に和らぎますが、数日経っても変化がない場合は歯科での診断が必要です。
歯周病・歯肉炎(歯ぐきからのトラブル)
歯ぐきの腫れや出血が目立つ場合、歯周病や歯肉炎の可能性があります。
歯ぐきがふくらむことで、歯が浮いているように感じるのです。疲れやストレス、口内ケアの不足も引き金になります。
予防には、丁寧な歯磨きと定期的な歯科検診が欠かせません。
根尖性歯周炎(神経を取った歯の奥に膿)
過去に神経を取った歯が再び痛む場合、根の先に膿がたまる「根尖性歯周炎」が疑われます。
痛みは奥深く、じわじわと響くように感じます。
放置すると骨まで炎症が広がるため、早めの受診が必要です。
歯ぎしり・食いしばり(無意識の力)
就寝中の歯ぎしりや、日中の無意識な食いしばりは、歯に過度な圧力をかけます。
その結果、歯根膜が圧迫され、浮いたような感覚が起きます。朝のあごの疲労感や歯のすり減りがサインです。
関連記事:ナイトガードで歯ぎしりを防ぐ方法
ナイトガード(マウスピース)や、日中の噛み癖の見直しが対策になります。
噛み合わせのズレ(偏った力の負担)
歯並びのズレや詰め物の高さの違いが、一部の歯に力を集中させます。この力の偏りが炎症を招き、歯が浮いたような違和感や痛みにつながります。新しく詰め物をしたあとや、親知らずが生えてくる時期にも起こりやすい症状です。
上顎洞炎(副鼻腔が原因の歯痛)
風邪やアレルギーで副鼻腔が炎症を起こすと、上の奥歯に違和感や痛みを感じることがあります。実際には歯に異常がない「関連痛」です。鼻づまりや頬の重さがある場合、耳鼻科での診察が必要です。
知覚過敏(冷たい刺激で歯が痛い)
冷たい飲み物や風がしみる場合、歯の表面のエナメル質が薄くなっている可能性があります。
象牙質が露出して、刺激に敏感になるのです。一時的な浮いた感覚も伴うことがあります
専用の歯磨き粉や、歯科でのコーティング処置で改善が期待できます。
ホルモンバランスの影響(生理・更年期と歯ぐき)
生理前や更年期にはホルモンの変化により、歯ぐきが腫れやすくなります。
その結果、歯が浮いたような違和感や痛みを感じることがあります。一時的とはいえ、歯周病を招きやすい状態でもあるため、いつも以上に口腔ケアに気を配ることが大切です。
ストレス・自律神経の乱れ(体からのSOS)
ストレスや過労は、体のバランスを崩すだけでなく、痛みの感受性も高めます。
自律神経が乱れると、歯ぐきの血流が悪くなったり、噛み締めが起きたりして歯の違和感へとつながります。
まずはしっかり休息を取り、深呼吸や軽い運動でリズムを整えましょう。
気象の変化・気圧(天気と痛みの関係)
雨の日や気圧の低下に合わせて、関節や歯に不調を感じたことはありませんか?「気象病」と呼ばれる状態で、特に副鼻腔や歯茎の違和感に影響します。
歯の重だるさや浮いた感覚が強く出るときは、漢方やツボ刺激が助けになることもあります。
非歯原性歯痛(原因が歯にないケース)
見た目もレントゲンも問題なしなのに、痛む。それが「非歯原性歯痛」です。
三叉神経痛、顎関節の不調、筋肉の緊張、さらにはストレス由来の痛みなど、原因は歯の外にあります。歯科で異常が見つからなければ、内科神経内科の診察も視野に入れましょう。
放置で治る? 受診の必要があるケース

歯が浮いた感じや噛むと痛い症状は、軽ければ数日で自然におさまることもあります。
ただし、以下のような状態が続く場合は早めに歯科を受診しましょう。
痛み・症状が数日以上続いている
歯が浮いた感じや痛みが3日以上続く場合は、自然に治る見込みが低くなります。
炎症や感染が進行している可能性があるため、自己判断で放置しないようにしましょう。
例えば、4〜5日たっても痛みが引かない、違和感が強くなるなどの変化があれば要注意です。
原因が虫歯や歯根の病気だった場合は、早期治療が治りを早くします。
症状が数日続く場合は、歯科での診察を受けましょう。
噛むたびに鋭い痛みがある
噛んだときにピリッと鋭い痛みが出るときは、歯根膜や神経に負担がかかっている可能性があります。
歯根膜炎や根尖性歯周炎が関係していることがあり、放置すると悪化する恐れがあります。
応急処置として、痛みが強い方の歯では噛まないように意識しましょう。
やわらかい食事に変える、冷たい飲食物を控える、夜間の歯ぎしり対策を試すのも有効です。
強い痛みが続く場合は、歯科での検査を受けてください。
歯茎が腫れている/膿が出る
歯茎が赤く腫れていたり、白い膿が出ていたりする場合は、歯周病や感染が進行しているサインです。
膿が出るということは、体が細菌と戦っている状態であり、自然に治るのを待つのは危険です。
腫れた部分を冷やすと一時的に楽になることもありますが、根本的な治療にはなりません。
膿が出ていたり、歯茎の腫れが引かない場合は、早めに歯科を受診しましょう。
顎が重い感覚や違和感がある
顎に重だるさを感じる場合、歯の炎症が周囲の骨や関節にまで広がっている可能性があります。
歯の奥から響くような痛みや、顎を開けにくいと感じる場合は特に注意が必要です。
違和感の原因が副鼻腔や筋肉の緊張による場合もあるため、口腔外科や耳鼻科との連携が必要なこともあります。
症状が軽くても、顎に違和感がある場合は歯科で相談してみましょう。
発熱や倦怠感を伴う
歯の痛みに加えて、37.5度以上の発熱や全身のだるさがある場合は、炎症が体全体に影響しているかもしれません。
体の免疫が戦っている状態であり、膿や感染が骨に及んでいることも考えられます。
歯の腫れと発熱が同時に出ているときは、痛み止めだけでごまかさず、医療機関を受診してください。
とくに高齢者や持病のある方は、全身症状が出た時点で早めの対処が必要です。
市販薬やケアで効果がない
歯の痛みがあるときに、市販の鎮痛薬や歯周病ケア用品を使う人は多いです。
ただし、2〜3日使っても痛みや違和感が軽くならない場合は、根本的な原因が市販薬では対応できない状態に進んでいる可能性があります。
例えば、痛みが少し引いたがまた戻る、夜になると痛みが強くなるといった場合も要注意です。
一時しのぎではなく、原因の治療が必要な段階と考えて、受診を検討しましょう。
自宅でできる対処法・セルフケア方法

歯が浮いた感じや噛むと痛い症状が出たとき、自宅でできる対処法を知っておくと安心です。
マウスピースの使用、ツボ押しやストレッチ、市販薬の使い方、リラックス法などを紹介します。
歯ぎしり・噛みしめへの対応(就寝時の意識・マウスピース)
歯ぎしりや噛みしめがあると、歯に負担がかかり、歯根膜が炎症を起こす原因になります。就寝中に無意識で起きるため、日中の対策が大切です。
たとえば、仕事中や家事の合間に「いま歯を噛んでいないか」を意識するだけでも予防になります。
夜間の対策としては、歯科で作るマウスピースが有効です。市販品もありますが、合わないと逆効果になる場合があります。
朝起きたときにあごが疲れているなら、就寝時の噛みしめが疑われます。違和感が続く場合は、歯科で相談してください。
ツボ押し(四瀆)・ストレッチ・温め
一時的な歯の浮きや違和感には、ツボ押しやストレッチ、温めが役立ちます。
とくに三焦経の「四瀆(しとく)」は、歯の違和感に効果的な場合があります。
手の甲の薬指と小指の間をひじ側に向かって押し、少し痛気持ちよい程度で10秒ほど刺激しましょう。
また、首や肩のストレッチも血流を改善し、あごまわりの筋肉の緊張を和らげます。
あごのつけ根やこめかみをホットタオルで温めるのも効果的です。緊張による痛みや違和感が軽くなることがあります。
市販薬(痛み止め・歯周病薬)の使い方と注意点
歯が浮いた感じや痛みが出たときは、市販薬を使って様子を見る人も多いです。
痛みが強いときには、イブプロフェンやロキソプロフェンなどの鎮痛薬が使われます。
ただし、2〜3日使っても痛みが引かない場合は、自己判断で飲み続けるのは危険です。
歯ぐきに異常があるときには、歯周病ケア用の薬用ジェルや洗口液を使う方法もあります。
いずれの場合も、症状が長引くようであれば早めに歯科を受診してください。
市販薬はあくまで一時的な対処です。
リラックス・ストレス軽減(自律神経ケア)
ストレスや自律神経の乱れは、歯ぎしりや食いしばりの引き金になることがあります。
根本的な解決には、日常生活の中でリラックスする時間を作ることが大切です。
ぬるめの湯船につかる、ゆっくり深呼吸する、眠る前にスマホを見ないなど、簡単な工夫で自律神経が整います。
寝る前にアロマをたく、クラシック音楽を聞くなども効果的です。
気づかないうちに歯やあごに力が入っている人は、まずは心身の緊張をほぐしてみてください。
歯科クリニックで行われる検査と治療法

歯が浮いた感じや噛むと痛い場合、歯科では精密な検査と症状に応じた治療を受けることができます。原因を正確に特定することで、効果的に改善を目指せます。
歯科での主な検査(レントゲン・CTなど)
歯科での主な検査には、視診・打診・レントゲン・CTなどがあります。
まずは口の中を直接確認し、必要に応じて画像検査を行います。レントゲンでは虫歯や歯周病の進行具合、骨の状態を確認できます。
CTは三次元的に骨や歯の根の形を把握できるため、複雑な痛みや違和感の原因をより詳しく調べたいときに使われます。
歯科医院によっては口腔内カメラや歯周ポケット検査も行われ、総合的に状態を把握します。検査によって原因が明確になると、適切な治療へとつながります。
治療方法(歯根治療/歯周治療/咬合調整など)
歯の状態によって治療法は異なります。
歯根の感染が原因の場合は、根の中をきれいにする歯根治療(根管治療)を行います。
歯ぐきの炎症がある場合は、歯石除去や歯周ポケットの洗浄といった歯周治療が行われます。
また、噛み合わせのズレが原因で痛みが出ている場合は、咬合調整が必要です。
詰め物や被せ物の高さを微調整したり、マウスピースを使って力のかかり方を整えます。
治療は1回で終わることもあれば、数回にわたる通院が必要になる場合もあります。
症状・原因に応じた治療の選択肢
症状や原因によって、治療の方法・期間・費用が変わります。たとえば、
- 歯根治療:1本あたり2〜4回、保険適用で数千円〜
- 歯周治療:歯石除去は1〜2回、保険内で数千円程度
- 咬合調整:軽度であれば1回で対応可能、保険で対応
- マウスピース治療:保険適用外で1〜3万円程度
治療方法は歯科医と相談し、自分の生活スタイルや経済状況に合う方法を選びましょう。説明を受けたうえで納得して進めることが大切です。
再発を防ぐ!日常でできる予防法

歯が浮いたような違和感や噛むと痛い症状は、日常の小さな習慣で予防できます。再発を防ぐために、毎日の行動を少しずつ見直していきましょう。
正しい歯磨き・デンタルケア習慣
再発を防ぐには、正しい歯磨きとケアを毎日続けることが基本です。歯ぐきの炎症や歯周病を防ぐためには、汚れをきちんと落とす必要があります。
具体的には、やわらかめの歯ブラシで力を入れすぎずに磨きましょう。1日2回、1回あたり3分以上を目安にしてください。フロスや歯間ブラシを使って、歯と歯の間も清潔に保つと効果的です。
週に1〜2回はデンタルリンスも取り入れましょう。定期的に歯科でのクリーニングを受けることも予防になります。正しいケアを習慣にして、再発を防ぎましょう。
関連記事:予防歯科
姿勢と生活習慣の見直し(スマホ首・猫背対策)
姿勢の悪さは、歯や顎に余計な力をかける原因になります。特にスマホ首や猫背は、噛み合わせや筋肉の緊張に影響します。
長時間うつむいた姿勢が続くと、首から顎、頭の筋肉が緊張しやすくなります。
これが噛みしめの原因になり、歯に負担がかかります。スマホを見るときは目線を上げ、30分に1回は首や肩を軽く動かしましょう。
また、椅子に座るときは深く腰をかけ、背筋を伸ばす意識を持ちましょう。寝具や枕の高さも見直してみてください。日常の姿勢改善が、口腔トラブルの予防につながります。
噛み癖や食いしばりの癖を知る
噛み癖や食いしばりを自覚することが、予防の第一歩です。
無意識のうちに歯を噛みしめている人は多く、自律神経や筋肉に影響します。
例えば、日中の集中時やストレスのある場面で上下の歯が当たっていないか意識してみましょう。本来、口を閉じているときも歯と歯は少し離れている状態が自然です。
気づいたら深呼吸して、顎の力を抜く練習を繰り返しましょう。夜間に歯ぎしりがある場合は、歯科でマウスピースを作ってもらうと有効です。癖を知って対策すれば、再発を防ぎやすくなります。
ストレスマネジメントと睡眠改善
ストレスは、噛みしめや歯の不調の原因につながります。体と心を落ち着かせる時間を持つことが予防になります。
毎日決まった時間に寝る、朝日を浴びる、カフェインやスマホの使用を夜は控えるなど、睡眠の質を上げる習慣を整えましょう。
入浴やストレッチで体温を上げてから寝ると、入眠がスムーズになります。
また、感情をノートに書き出す、軽い運動をする、アロマを取り入れるなどもストレス対策になります。自律神経のバランスを整えることが、歯や顎の健康にもつながります。
歯が浮いた感じがする時のよくある質問

歯が浮いたような感覚や噛むと痛いとき、どう対応すべきか迷う方へ。よくある疑問を簡潔にまとめました。
Q. 自然に治ることはありますか?
軽い疲れやストレスが原因なら、数日で治まることもあります。ただし、3日以上続く場合は歯科で診てもらいましょう。
Q. 歯医者に行かずに治す方法はありますか?
マウスピースやツボ押し、やわらかい食事で一時的に楽になることもあります。改善しない場合は歯科を受診してください。
Q. 肩こりやストレスと関係あるの?
あります。緊張やストレスが食いしばりを引き起こし、歯や顎に負担がかかることで違和感につながることがあります。
Q. 何科に相談すればいい?
まずは歯科を受診しましょう。原因によっては、口腔外科や耳鼻科と連携してもらえる場合もあります。
まとめ|歯が浮いた感じ・噛むと痛いあなたが今すぐできること
最後にもう一度、歯が浮いた感じや噛むと痛いときの対処法をまとめておきます。
- 原因を知る:歯根膜炎や歯周病、食いしばりなどさまざまな原因がある
- 症状をセルフチェック:痛みの場所、期間、歯ぐきの状態などを確認
- 自宅での対処法:ツボ押し、ストレッチ、マウスピース、市販薬の使用など
- 歯科での治療:レントゲン検査、歯根治療、咬合調整など症状に応じた処置
- 予防法を実践:正しい歯磨き、姿勢の改善、ストレス管理で再発を防ぐ
気になる症状があれば、まずはセルフチェックから始めてみましょう。
状態が続くようであれば、無理せず歯科で相談してみてください。
毎日のケアと少しの意識で、痛みのない快適な口元を保てますように。
デンタルオフィス虎ノ門は駅近で便利!
- 日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」より徒歩1分
- 銀座線「虎ノ門駅」より徒歩6分
当院、医療法人歯科ハミールの分院も、今後共よろしくお願いいたします。
この記事を書いた人

デンタルオフィス虎ノ門 院長 柳瀬賢人
所属学会・勉強会
- MjARSの主宰(歯科医師の勉強会)
- M:ALT’s(@土屋歯科クリニック&works)所属
- SJCD(日本臨床歯科学会)会員
- ITIベーシック・アドバンス サティフィケイト
経歴
- 東京医科歯科大学 卒業
- 名古屋大学 口腔外科
- 歯周病インプラント専門医Jiads講師のもとで勤務
- 医療法人複数歯科医院勤務
- 医療法人歯科ハミール デンタルオフィス虎ノ門院 院長就任
出身高校
- 愛知県立明和高等学校