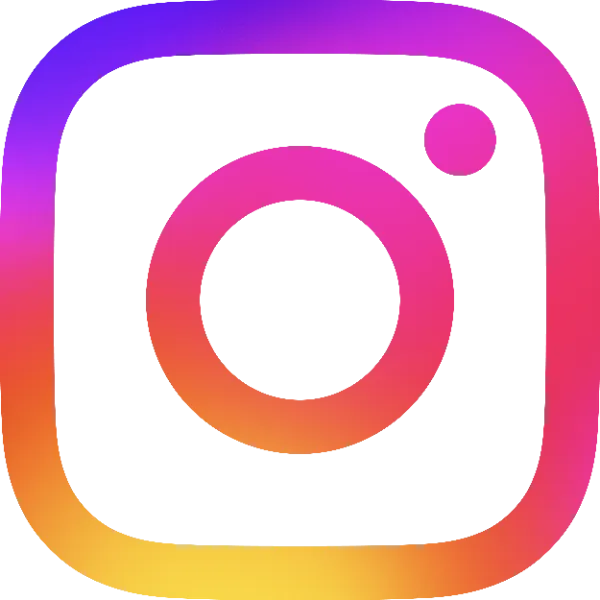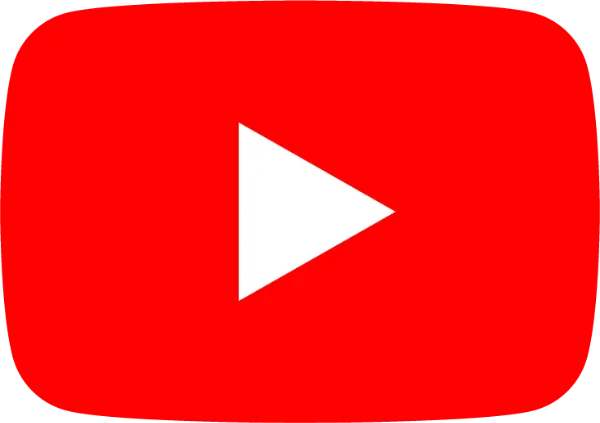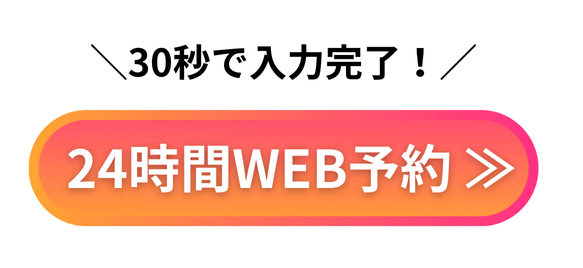定期健診でクリーニングと歯のチェックを行うことにより、虫歯や歯周病の予防、早期発見をすることができます。
定期健診を受けてきた方と、受けてない方とでは80歳になる頃には残る歯の本数が倍違ってくると言われています。
定期健診を受けていない80歳の平均の歯の本数はわずか9本しか残りません。
人生100年時代と言われる中、歯が少なくなり咬めない人生は悲しいですよね。そこで、歯医者で行う定期健診でのクリーニングについて解説します。
目次
保険適用で歯のクリーニングを受ける流れ

歯のクリーニングの前にレントゲン撮影を行ってからクリーニングを受けることをお勧めします。
レントゲン撮影は保険診療で約¥1,200で歯石のついている場所や歯周病の進行具合を目で見て分かるものです。
また、虫歯の有無も分かります。お口の中を目で見て分かる情報とレントゲンから得られる情報は異なるため、どちらかが欠けると見落としの原因になります。
その後、クリーニングに進むのですが保険診療のルールがあります。
保険診療のルール上の処置内容では、①歯茎の検査②お口の中全体の明らかな歯石取り③歯茎の再検査④歯茎の腫れが残っている箇所の歯茎の中の集中的な歯石取り⑤定期健診という流れです。
③の歯周病の再検査で問題がなかった時は、④をせずに⑤定期健診をすすめます。
歯のクリーニングの保険適用の料金

歯のクリーニングは内容によって保険適用の有無や料金が異なります。
一般的に、歯周病や歯石除去を目的とした処置は保険適用となり、3割負担の方でおおよそ¥2,000~¥3,000程度が目安です。
保険診療では、歯科医師の診断に基づき、スケーリング(歯石除去)や歯周ポケットの検査が行われます。
ただし、着色汚れの除去やPMTC(専門的な機械清掃)など見た目を目的としたケアは自費扱いになることが多く、その場合は¥5,000以上かかることもあります。
医院によって内容や金額が異なるため、事前に確認することが大切です。
歯のクリーニングの保険適用外の料金
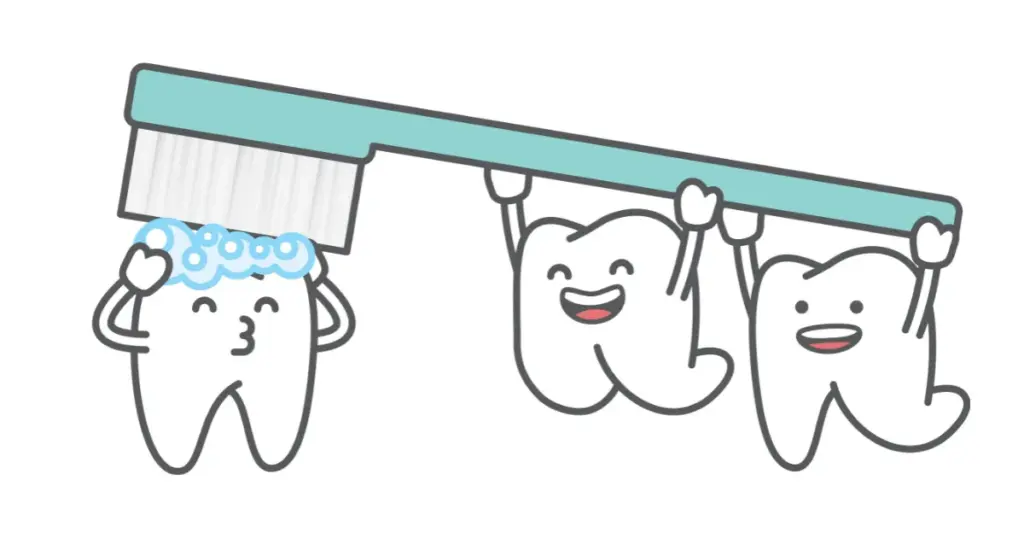
保険外のクリーニングは保険のルールに縛られずクリーニングを行うことができます。
当院ではパウダークリーニングと言われる、歯の着色に特化したクリーニングや、通院回数を減らして集中的な歯石取りを行うFMD(フルマウスディスインフェクション)というプランがございます。パウダークリーニングは歯石取りも行って約¥10,000で行っております。
歯のクリーニングにかかる時間
一般的には30分程度のことが多いですが、歯石の量などにより前後します。
歯のクリーニングの内容

歯のクリーニングの内容は以下のとおりです。
- 歯周ポケット検査
- 染め出し検査
- 歯垢や歯石の除去
- フッ素処理
- 表面のポリッシング
順番に解説します。
歯周ポケット検査
歯茎の腫れ具合を測定する検査です。歯茎が腫れているほど、歯と歯茎の境目に深い溝を作るので、細菌が溜まりやすくなっています。
染め出し検査
歯の汚れを染め出すことによって、目で見てどこに磨き残しがあるか確認できます。また、磨き残されている割合を計って歯磨きの上達度を記録します。
歯垢や歯石の除去
歯垢とは、歯に付着した最近の塊です。磨き残しが1日程度放置されると歯垢になります。細菌が集まりバイオフィルムと言われるバリアを形成するため、うがい薬などでは効果がなくなります。専門的なブラシなどを使って歯垢を除去していきます。
歯垢がされに放置されると歯石と言われるものになります。歯石はかなり硬くここまで進んでしまうと歯ブラシでは取れません。また、歯石の表面はざらざらしており、より歯磨きで細菌を取り切れなくなりどんどん歯石は拡大していきます。歯石は超音波の器具で取ったり、鎌状のスケーラ-というもので除去したりします。
フッ素処理
虫歯のリスクが高い方や歯が生えたてで弱い状態のお子様にフッ素を塗ることで歯を丈夫にします。塗った後は30分程度、うがいや飲食は控えた方がよいです。
定期検診とクリーニングの違いとは?

定期検診とクリーニングの違いをいかにまとめました。
目的の違い
歯医者で行う「定期検診」と「クリーニング」は、目的が明確に異なります。
定期検診の主な目的は、むし歯や歯周病の早期発見・予防です。
自覚症状が出る前の小さな異常を見逃さないために行われます。
一方で、クリーニングは歯石やプラークといった汚れを除去し、口腔内を清潔に保つことが主な目的です。
どちらもお口の健康維持には欠かせませんが、定期検診が「病気を見つけること」に重きを置くのに対して、クリーニングは「病気を防ぐための清掃」が中心となります。
実施内容の違い
定期検診では、歯科医師や歯科衛生士が口腔内の状態をチェックし、むし歯の有無、歯周ポケットの深さ、歯のぐらつきなどを確認します。
必要に応じてレントゲン撮影も行い、目に見えない部分の異常を調べることもあります。
一方、クリーニングは専門の器具を使って、歯に付着した歯石やバイオフィルムを除去する処置です。
PMTC(プロによる機械的歯面清掃)やスケーリング、仕上げのフッ素塗布などが含まれ、見た目の清潔感や爽快感も得られます。
受診頻度の違い
定期検診の受診頻度は、お口の状態に応じて3〜6ヶ月に1回が推奨されています。
むし歯や歯周病が進行する前に兆候を捉えるためには、定期的なチェックが欠かせません。クリーニングの頻度も似ていますが、歯石がたまりやすい人や着色が気になる方は、1〜3ヶ月に1回のペースで受ける方もいます。
逆に、歯の状態が良好であれば半年に一度でも十分なこともあります。自分に合った間隔は、歯科医師のアドバイスをもとに決めるのが安心です。
歯を常に綺麗にするために意識するべきこと

歯を常に綺麗にするために意識するべきことは以下のとおりです。
- 正しいブラッシング習慣を身につける
- フロスや歯間ブラシでのケアも忘れずに
- 定期的なプロケアを受ける
順番に解説します。
正しいブラッシング習慣を身につける
毎日の歯みがきは、歯を綺麗に保つための基本です。
しかし、間違ったブラッシングでは汚れが落ちきらず、逆に歯や歯茎を傷つけてしまうこともあります。
大切なのは、「力を入れすぎない」「毛先を歯と歯茎の境目にあてる」「1本ずつ丁寧に磨く」など、正しい磨き方を意識することです。
食後すぐに磨く習慣や、1日2〜3回のブラッシングを継続することで、プラーク(歯垢)の蓄積を防ぎ、口臭や着色汚れの予防にもつながります。
フロスや歯間ブラシでのケアも忘れずに
歯ブラシだけでは、歯と歯の間の汚れを完全に落とすことはできません。
特に歯垢や食べかすが残りやすい歯間部は、デンタルフロスや歯間ブラシを使って丁寧に清掃することが重要です。
1日1回、夜の歯みがき後に使用する習慣をつけると効果的です。
歯と歯の間のケアを怠ると、むし歯や歯周病の原因にもなり得ます。最初は面倒に感じるかもしれませんが、使い慣れれば数分でできるようになり、清潔感のある口元を保つのに大きく役立ちます。
定期的なプロケアを受ける
セルフケアを徹底していても、すべての汚れを取り除くのは難しいものです。
特に歯石は、時間が経つとブラッシングでは落とせなくなり、口臭や歯周病の原因になります。
そうしたリスクを防ぐためにも、歯科医院での定期的なクリーニングや定期検診が欠かせません。
専門的な機器でのケアにより、歯の表面の着色や隠れた歯石を取り除き、ツルツルの状態を維持できます。最低でも半年に一度の受診を習慣にすることが、美しい歯を保つ近道です。
まとめ
歯医者でのクリーニングを受けることで、歯の寿命を延ばすことができます。是非、歯医者でのクリーニング、定期検診に通われてみてください。また、歯医者での保険適応のクリーニングにはルールがありますので、ご不明な点等ございましたら、かかりつけの歯科医院で聞いてみてください。
デンタルオフィス虎ノ門は駅近で便利!
- 日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」より徒歩1分
- 銀座線「虎ノ門駅」より徒歩6分
当院、医療法人歯科ハミールの分院も、今後共よろしくお願いいたします。
この記事を書いた人

デンタルオフィス虎ノ門 院長 柳瀬賢人
所属学会・勉強会
- MjARSの主宰(歯科医師の勉強会)
- M:ALT’s(@土屋歯科クリニック&works)所属
- SJCD(日本臨床歯科学会)会員
- ITIベーシック・アドバンス サティフィケイト
経歴
- 東京医科歯科大学 卒業
- 名古屋大学 口腔外科
- 歯周病インプラント専門医Jiads講師のもとで勤務
- 医療法人複数歯科医院勤務
- 医療法人歯科ハミール デンタルオフィス虎ノ門院 院長就任
出身高校
- 愛知県立明和高等学校